
調査地を北側の山の斜面から眺めた風景
(谷の入り口の中央に見える赤い屋根のあたりが般若院の境内)
ヒキガエルは、一般にガマガエルとも呼ばれている大型のカエルで、全身にいぼ状隆起をもち毒液を分泌することで有名である。アズマヒキガエル(Bufo japonicus formosus)は、日本産の代表的なヒキガエルであるニホンヒキガエルの1亜種とされており、主として本州の東半分の地域に分布し、平野部から山地まで幅広い環境に生息している(前田·松井, 1989)。関東地方の平野部では、早春2·3月頃になると多数のヒキガエルが池に集まり繁殖活動を行い、「ガマ合戦」として古来より人々に親しまれてきた。以前はガマ合戦の見られる繁殖場が各地に知られていたが、近年大都市近郊の土地開発が進むに従い、そのような場所は著しく減少してしまった。残念ながら、東京や神奈川の都市郊外では特にこの傾向が強く、ガマ合戦の見られる場所を探すのは大変困難な状況にある。
幸いにも、山北町岸のヒキガエル集合地は神奈川県の天然記念物に指定されており、現在でも多数のヒキガエルが繁殖活動を行っている。しかしながら、1972年に天然記念物に指定されて以来、この場所のヒキガエル繁殖個体群について充分な調査が行われているとは言い難い。山北町岸周辺でも近年環境の変化が予想されることもあり、ヒキガエルの繁殖個体群を維持し保護していくためには、この個体群の現状を適切に把握し、木目細かな対策を講じていく必要があるだろう。そのためにも、彼らの詳細な生態調査が早急に望まれる。
我々は、1992年および1993年の主として繁殖期を中心に、神奈川県山北町岸のヒキガエル集合地の繁殖個体群の生態調査を行い、繁殖活動の現状および繁殖個体の分散過程について情報を得ることができたので、ここに報告する。なお、この調査は三井造船株式会社による山北町丸山地区開発に伴う、神奈川県指定天然記念物「山北町岸のヒキガエル集合地」が受ける影響調査として行われたものである。
1992年3月から7月、および1993年2月下旬から4月上旬にかけて、 神奈川県足柄上郡山北町岸1640番地の般若院境内(標高100m)および その周囲の地域において調査を行った。

調査地を北側の山の斜面から眺めた風景
(谷の入り口の中央に見える赤い屋根のあたりが般若院の境内)
般若院境内には西側と南側に計2ヵ所の池があり、どちらの池 でもアズマヒキガエルの繁殖が確認されている。池は双方とも長さ6-7m、幅2-3m、深 さは20-40cm程度の小さなもので、約30m離れた場所に位置している。ここで は仮に西側の池をA池、南側の池をB池と呼ぶ。今回の調査の対象であるアズ マヒキガエルの他に、A池ではヤマアカガエル(Rana ornativentris ) ·ツチガエル(R. rugosa )·シュレーゲルアオガエル(Rhacophorus schlegelii )、B池ではヤマアカガエル等の両生類の 生息が確認されている。また、B池では鯉が飼育されている。

ヒキガエルの繁殖池(B池)
1992年の調査は、繁殖活動の開始の兆候が確認された3月11日より3月19日までの9日間、般若院境内の2ヵ所の池及びその周辺にて繁殖個体の調査を毎日行った。昼夜を問わず(6時-23時30分)池を中心に境内を随時巡回し、目撃した ヒキガエルの個体数を数え、その位置を地図上に記録した。その際、A池に おいて水温 · 気温も同時に測定し記録した。出現個体数調査の際発見 された未標識個体は、原則としてすべて捕獲するよう努力した。ただし、産卵 直前および産卵中のペアは、その産卵行動に影響を与えるのを避けるため捕獲 しなかった。捕獲した個体は、性を記録し、体長(頭胴長) · 脛骨長をノギスで1mmまで計り、体重をバネ秤で5gまで測定した。すべての個体は指 切り法で標識し、さらに番号を記したタグ(1.5×1.5cmの薄いゴム板) を頭部に瞬間接着剤にて接着することにより個体識別を行った。これらの個体 は上記の作業後、出来るだけ速やかに捕獲地点に放した。また、繁殖活動の日 周パターンを調べるため、3月13日17時30分から14日5時30分まで終夜観察を行 い、2時間毎に出現個体の調査を行った。
1993年の調査では、2月下旬から適宜調査地に通い、繁殖個体の出現状況を 確認し、池の水温および周辺部の気温を測定した。繁殖個体の出現が確認され た3月13日以降は、出現個体の見られなくなった3月末まで毎日調査を行った。 1993年の調査では、出現個体数調査を原則として日没の前後2回づつ、一日に 計4回定時に行った(14時00分, 16時00分, 19時00分, 21時00分)。その際捕獲 された個体は、すべてタグを頭部に装着し個体識別を行い、指切りは行わなか った。ただし、タグが脱落した時に備えて、後肢の水掻きの一部に切れ込みを 入れ、すでに捕獲標識済の個体であることを確認できるようにした。
般若院から北西に直線で350m離れ、低い尾根を一つ隔てた三尋木氏宅の池 (山北町岸1714番地)も同じくヒキガエル産卵池として県指定天然記念物に 指定されているが、1992年の調査時には土手が壊れて水がほとんどなく産卵は 期待できない状態だった。このため、調査期間中に3回、様子を見に行くのにとどめた。1993年の繁殖期には修理がなされ、産卵に十分な量の水がたまっていたので、 3月10日から4月4日まで(うち3月12日から29日は連日)17時00分に 観察と水温測定を行った。ただし、1992·1993年とも、この池には数頭のオスが 一時的に出現したのみで、産卵も確認できなかったので、本稿では三尋木氏宅の池の 繁殖集団については特に触れないことにする。
1992年の調査の際個体識別のため各個体から切除した指骨は、年齢推定に用 いるため10%ホルマリンで固定し研究室に持ち帰った。5%希硝酸で脱灰後、 凍結ミクロトームで切片を作成し、ヘマトキシリンで染色後顕微鏡下で観察し、 年齢査定を試みた。
1992年には、上記の繁殖個体調査の際捕獲された個体から適当な個体を選び、 小型の発信器(2.2×1.4×0.5cm、重量4.1g)をゴム製の腰バンドにて腰に 装着し捕獲地点に放した。ただし、長期間の腰バンドの使用により皮膚が擦れ てきた場合は、腰バンドの使用を中止し、背中の皮膚に木綿糸で発信器を縫い つけ装着し直した。また、調査途中で脱落したり装着個体が死亡した場合は、 出来るだけ発信器を回収し、その後発見された未装着個体に再度装着した。

発信機を腰に装着したヒキガエルの繁殖ペア
(上の黄色の個体がオス、下の赤っぽい個体がメス)
放逐後は、主としてループアンテナを用い、またループアンテナで電波が傍 受できない時は八木アンテナを併用して方向探索(方探)し、発信器を装着し た個体の位置を確定して地図上にプロットした。その際、出来るだけ彼らを直 接目で確認するよう努め、発見時のヒキガエルの活動状況および周囲の状況を 記録した。前述した繁殖個体調査期間中は、毎日数回昼夜を問わず方探を行っ たが、繁殖活動が終了した3月下旬以降は原則として週に1回、昼間に方探を行 った。

分散した個体を電波を頼りに追跡しているところ
(二人のアンテナの先の草むらにヒキガエルが潜んでいる)
6月上旬になると発信器の電池切れ等によって、電波を傍受出来なくなる個
体が現れ始め、追跡できる個体の数が徐々に減ってきたため、7月一杯で調査
を打ち切った。
今回の調査では、1992年には合計126頭(♂95頭、♀31頭)、1993年には 113頭(♂77頭、♀36頭)の繁殖個体を捕獲することが出来た。繁殖個体の体 長は、オスで90-170mmで平均130mmほど、それに対しメスは少し大きく 110-160mmで平均140mm弱であった(図1)。アズマヒキガエルの個体群の平均体長に は地理的変異が見られることが知られている(松井, 1987)。すなわち、緯度 が低い南の個体群ほど体が大きく、緯度の高い北の個体群ほど体が小さい。山 北の個体群の平均体長はほぼこの傾向にのっており、アズマヒキガエルの中で は比較的体の大きな個体群であると言える。
体重は、オスで100-400gと個体による差が大きく、平均は1992年には236.7g (SD=54.1, N=95)、1993年には200g以下の軽い個体の割合が増え、平均値は少し軽くなり 192.8g(SD=61.0, N=77)となった。 体長の場合と同様、メスの方が体重も重く150-400gで、平均はそれぞれ320.3g (SD=61.8, N=19)と271.2g(SD=57.4, N=28)であった。ただし、 メスの場合は産卵後大きく体重が減少するので、産卵前の 値が得られている個体についてのみ計算に用いた。
体長·体重を少し詳しく見ると、年により体サイズの頻度分布のパタ ーンに違いが見られることが分る。1992年には、比較的小型の個体が オス·メスとも少なく、大きな個体の占める割合が1993年に比べて大きかった。これは、年による成長の差を反映したものと考えるよりも、繁殖個体群への新 成熟個体の加入の違いを反映したものと考えるほうが無理がないように思う。 すなわち、1992年には何らかの理由で新成熟個体の加入が少なく、 その年の繁殖個体は高年齢の大きな個体の比率が高かったのに対し、1993年には体のまだ小さい新成熟個体が順調に加入したため、平均体サイズの減 少が見られたと考えられる。ヒキガエルなどの大型のカエル類では、成熟する まで生き残れた個体はその後の生残率が比較的高いと予想される(繁殖個体 の生残率については後述する)。しかしながら、卵から幼生期および変態後の まだ体の小さな時期には、かなり死亡率が高く、また年次変動も大きいことが 予想される。そのため、繁殖個体群の個体群サイズや構造も年により大きく変 動する可能性が高いと考えられる。
多くのカエル類では、指骨に成長停滞期に形成されると考えられる成長線 (樹木の幹に形成される年輪に相当するもの)が見られるので、これを観察す ることによりその個体の年齢を推定することができる (草野·宮下, 1990; 草野他, 1991)。そこで、1992年の調査で繁殖個体から採集した指骨を用いて、一部の個 体の年齢推定を試みた。ヘマトキシリンで染色した指骨の切片を顕微鏡下で観 察したところ、鮮明に染色される成長線が観察され、その数を数えることによ り、合計22頭(♂20頭、♀2頭)について年齢を推定することができた。オ スは1から6歳まで見られ、4歳の個体が最も多かった(図2)。ここで特に注目 されるのは、体長94mmと106mmの2頭のオスが1歳と推定されたことである。 ヒキガエルは、5月頃10mmにも満たない小さな体長で変態上陸するが、その後1 年で100mmまで成長する個体が少数だがいるようだ。ヒキガエル類の成長は他 のカエル類と比較して一般に速いが、山北の個体群の成長速度は、その中でも かなり速い部類に入るだろう。
一般に両生類では、成熟し繁殖を始めると成長速度が著しく低下することが 知られている。そこで、指骨の 成長線の径の成長パターンから個体の成長を推定し、成長速度が著しく低下 する時期から繁殖開始年齢を推定した。その結果、オスは1-4歳、ほとんどの個体 は2歳で繁殖に参加すると推定された(図2)。メスは調査個体数が少なく参考 程度にしかならないが、オスと大きな差は見られず2歳で繁殖を始める個体が いると推定された。東京の港区のアズマヒキガエルでは、オスは2-3歳、メス は1年遅れて3-4歳で成熟し繁殖に参加する(久居, 1981)。金沢の ニホンヒキガ エルでは、オスは3歳以上、メスは4歳以上で繁殖に参加すると報告されている (奥野, 1984c)。これらに比べて、山北の個体群では早熟の傾向が強く見ら れるが、体サイズは決して小さいわけではなく、変態後の幼体の成長がかなり 速いことを示している。
前節(4.1.1.節)でもすでに触れたが、1992年には新成熟個体の加入が 少なかったと思われるが、年齢分布の推定結果もこれを支持している。オスの繁殖 開始年齢はほぼ2歳と推定されるので、安定個体群では 2歳の個体が最も多く、3歳以上の個体の数は次第に減少していく年齢構造を示 すはずである。しかしながら、実際は図2に示すように2歳以下の個体は極めて 少なく、むしろ4歳の個体が最も多く見られた。このことは、1992年には若い 新成熟個体の加入がほとんどなく、繁殖個体群は4歳程度の比較的老齢な個体 によって構成されていたことを示している。これは、何らかの理由で、 1989-1990年の繁殖が失敗した結果と思われる。我々は、1992年の繁殖期にA池で産 卵された卵がまったく孵化せず、繁殖に失敗したのを観察したが、同様のこと が以前にも起こっていたのかもしれない。1992年には幸いB池では幼生が孵化 し、変態上陸した幼体を確認することもできた。また、1993年には 新成熟個体と思われる 個体の加入も少なからず見られたことから(図1)、繁殖が最近 毎年失敗しているということではないようだ。しかしながら、1992年のA池の卵の全 滅に水質悪化が関係している可能性が考えられるが、はっきりした原因 が不明な点が気に掛かるところである。繁殖個体群の保護のためには、今後繁 殖失敗の原因を解明していくことが不可欠であろう。
| 項目 | A池 | B池 |
| 一般細菌(個/ml) | 1,600 | 290 |
| 大腸菌群(個/ml) | 70 | 100 |
| 硝酸性窒素および | 0.2 | 0.2 |
| 亜硝酸性窒素(mg/l) | ||
| 塩素イオン(mg/l) | 5 | 6 |
| 有機物など(mg/l)* | 56 | 8.8 |
| pH値 | 6.6 | 7.3 |
| アンモニア性窒素 | 検出せず | 検出せず |
| 陰イオン活性剤(mg/l) | 0.2未満 | 0.2未満 |
| * 過マンガン酸カリウム消費量 | ||
両生類の卵の孵化率に影響を与えると考えられる水質について検討するため、 1993年4月には足柄上保健所に依頼し、A·B両池の水質検査を行った。 その結果、A池で一般細菌数、有機物量が 多く、pHが酸性に傾いていることを除けば、特にカエルの生息に悪影響を与える と思われる要因は見出せなかった(表1)。実際、この年もB池では変態上陸個体が 確認され(般若院住職の話)、A池でも6月に多数の幼生が確認されているので、 1993年には両池とも繁殖に成功したものと思われる。卵が全滅した1992年のA池の 水質がどうであったのか、大変興味深いところである。
今回の調査では、出現した個体をできるだけ捕獲するよう努力したが、必ず しもすべて捕獲できたわけではなかった。そこで、総出現個体数を推定するた め、繁殖シーズン中の捕獲率を標識再捕データより推定した。1992年には、繁殖池に出現したことが確認できたオス94頭、メス28頭の平均再捕獲(視認)回 数は、それぞれ3.2±3.1(SD)、0.9±1.1(SD)であった。1993年は、オス 75頭、メス36頭の平均再捕獲回数は、それぞれ10.1±9.2(SD)、1.6±2.0(SD)であった。これらの標識放逐した個体のうち、1回 以上シーズン中に再捕 獲された個体の割合(再捕率)を計算した(表2)。再捕率はオスではかなり 高くほぼ 80%以上の値を示したが、メスではオスより有意に低いことが分っ た。これは、両者の繁殖場への出現様式の違いを反映したものと考えられる (4.2.2.節参照)。
| 標識数 | 再捕数* | 再捕率 | 性差の検定** | ||
| P | |||||
| '92 | ♂ | 94 | 74 | 0.79 | 0.008 |
| ♀ | 28 | 14 | 0.50 | ||
| '93 | ♂ | 75 | 68 | 0.91 | 0.029 |
| ♀ | 36 | 26 | 0.72 | ||
| * 1回以上再捕獲された個体数 | |||||
| ** Fisherの正確確率検定 | |||||
この再捕率を捕獲率 p と見なし、以下の式から総出現個体数の 推定値[^N]を求めた。
|
ただし、 NC は総捕獲数を表す。その結果、この池には、90-120頭のオス と50-60頭のメスが集まり、合計140-180頭の個体が繁殖活動を行っていると 推定された(表3)。1992年に比べて、1993年は総捕獲数および推定出現数と も少し少ないようだ。また、ヒキガエルでは一般に繁殖個体群の性比はオスに 偏る傾向が知られているが、山北の個体群でも、やはりオスの方が約2倍程度 メスに比べて多いことが分った。
| 総捕獲数 | 推定個体数 | |||
| '92 | '93 | '92 | '93 | |
| ♂ | 95 | 77 | 120.2 | 84.6 |
| ♀ | 31 | 36 | 62.0 | 50.0 |
| 合計 | 126 | 113 | 182.2 | 134.6 |
ヒキガエルの繁殖個体群の性比がオスに偏る理由として、成熟年齢や繁殖個 体の死亡率の性差や、毎年の繁殖参加率がオスに比べメスでは低く、数年に 一度しか繁殖に参加しない個体が多いことが挙げられている(久居, 1981)。し かしながら、山北の個体群では、後述するシーズン間の標識再捕調査の結果か ら、年間の生残率や繁殖参加率に性差があるとは考えにくい(4.5.1.節参照)。 繁殖個体群の性比の偏りは、主に成熟年齢の性差により生じたものと考えるの が妥当だと思う。すなわち、オスでは早いものは1歳で繁殖を始め、ほとんど の個体が2歳までに成熟する。それに対し、メスは1歳で繁殖を開始するものが いるとは考えがたい。ほとんどの個体は2歳から3歳で繁殖を始めるのではない だろうか。成熟の遅れに伴い、その期間にも死亡が起こるため、結果としてメ スの個体数はオスに比べて少なくなっているのかもしれない。実際、成体の年 間死亡率は約50%と推定されるので(4.5.1.節参照)、メスの成熟が1年遅れ れば繁殖個体の数は半分に減り、性比の偏りの大部分を説明可能である。いず れにしても、より多くの個体(特にメス)について、指骨の骨組織を用いた 年齢査定を行う必要があるだろう。
A·B両池における繁殖活動の経時変化のパターンを知るために、日没後の 定時センサス時における池への出現個体数の経日変化を見た(図3,4)。1992年には、B 池のほうがわずかに早く活動が始まったが、全体としては池間で大きな差はな く、3月12日より17日まで6日間繁殖活動が観察された(図3)。ただし、実質 的には3月13日から15日までの3日間に集中しており、この年は繁殖シーズンが かなり短かった。それに対し、1993年は全体的に繁殖活動がかなり長引き、池 間でも開始時期がかなり違ってしまった。B池では3月13日に繁殖個体が出現 し、繁殖活動は約2週間程続き月末の27日頃まで活動が観察された。A池では 開始がかなり遅れ、18日から29日まで繁殖個体の出現が見られた(図4)。
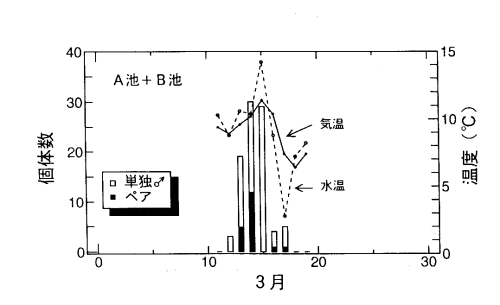
Figure 3:
日没後の定時センサス時における出現個体数の経日変化(1992年).
山北町岸の繁殖個体群については、1974年にも繁殖活動の調査が 行われている(松川, 1974)。それによると、例年は3月下旬に短期間出現するのが 通例だが、1974年には3月13日に初めて繁殖個体が池に姿を現し、 その後3月31日まで姿が見られたという。この産卵期の長さは、1993年にほぼ匹敵し、 山北町では2週間以上にわたる繁殖活動が必ずしも珍しいものでないようだ。
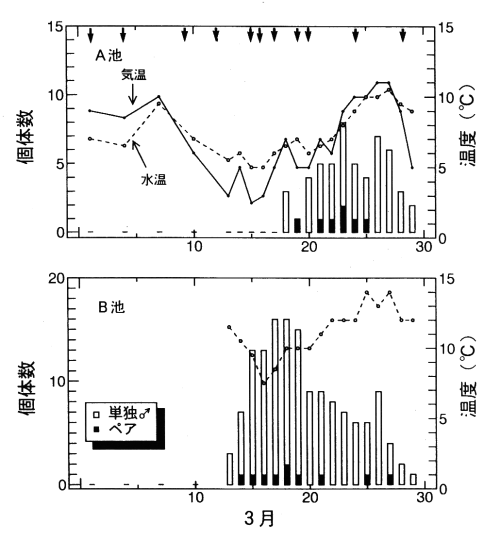
Figure 4:
日没後の定時センサス時における出現個体数の経日変化(1993年).
矢印は降雨のあった日を示す.
ヒキガエルの繁殖活動の開始時期や繁殖シーズンの長さが、同じ 個体群でも年により異なり、また同じ年でもわずか数10mしか離れていない池 間でかなり異なることが分ったが、なぜこのような違いが見られるのだろうか。 ヒキガエルの繁殖開始には彼らが、冬眠している場所の地温が重要であると言 われている(例えば、久居·菅原, 1978)。 確かに、本調査地でも南向 きで日当たりの良い庭にあるB池の方が、建物と尾根の陰になり日当たりの悪 いA池よりも早目に繁殖が始まる傾向が見られた。温度が繁殖の開始に重要な 影響を与えているのは確かだろう。また、繁殖シーズンの長さにも温度変化の パターンが重要な影響を与えているように思える。 すなわち、1993年には、繁殖期が始まりかけた3月10日頃から低温が続き、雪さえ降ったことが、 産卵期の長期化に影響を与えていると推測される。 1992年には全般的に気温が高かかったため、ほとんどの個体が短時間のうちに冬眠から 覚めて産卵行動を開始したのに対し、1974年や1993年には冬眠覚醒の閾値近くの 比較的低い温度が続いたため、個体の感受性に応じて産卵行動に入る時期が大きく バラついたのではないだろうか。そのため、産卵が同調せず繁殖シーズンが 長期化したと考えられる。
次に繁殖活動の日周変化について見てみたい。1992年の繁殖活動が本格的に 開始された3月13日の夕方から翌朝まで終夜観察を行ったが、この結果と随時 行った出現個体数調査の結果を図5に示した。また、1993年の一日に4回行った 定時センサス時の出現個体数の変化を図6に示した。一般にヒキガエルなどの 両生類は夜行性の傾向が強いと言われているが(例えば、芹沢·金井, 1970)、今回の調査では明瞭な日周パターンを観察することは出来なかった。 調査個体群のヒキガエルは、明るい日中でも活発に繁殖活動を行っているのが 観察され、今までの研究結果とかなり異なったものとなった。これは、周囲の 環境と関係があるのかもしれない。3月頃の般若院の境内は、日中でも比較的静 かで人の気配も少なく、繁殖個体の活動を妨げないのだろう。東京都港区の自然教育 園でも、ヒキガエルの繁殖活動は日没後に行われるのが普通だが、林の奥など 人為的影響の少ない場所では、日中でも抱接中の個体が多く見られるという (久居·菅原, 1978)。
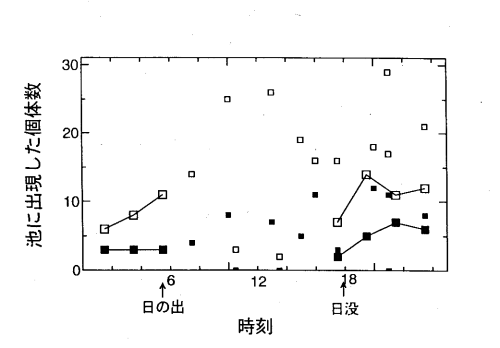
Figure 5: 繁殖ピーク時の出現個体数の日周変化(1992年).
白抜きの四角は単独オスを, 黒四角はペアの数を示す.
実線で結んだ四角は終夜連続観察の結果を示す.
繁殖個体の活動に特に日周性が見られず、昼でも夜でも活動が活発に見られ たが、明け方など気温が下がる時期には若干出現数が減る傾向が図5からも見 られる。そこで、1992年3月13日から15日までの繁殖のピーク時における気温 と出現個体数の関係を分析したところ、有意な正の相関が検出され (rs=0.60, N=39, P < 0.001)、 また1993年にも同様な傾向が観察された。ヒキガエルの繁殖活動は温度に強く 影響を受けることが分った。
調査期間中に繁殖活動のために出現した個体の、シーズン中に利用した繁殖 池を見ると、個体により利用する池がはっきり分れていることが分る(図7)。 すなわち、一頭の個体はどちらか一方の池のみに出現し、両方を行き来する個 体はオス·メスとも極めて少なかった。A·B両池間の距離は 約30mと近く、目と鼻の先にあるにもかかわらず、両池間で個体の交流が極めて少 ないのは驚きである。特に1993年には、繁殖シーズンが長期化し、オスの中に は一週間以上繁殖池に出現し続けた個体もかなりいたのだが、出現場所を換え る個体はやはり少なかった。
次に、各個体の繁殖池の利用をシーズン間で比較してみよう。2シーズン連 続して繁殖池への出現が確認されたオスで、1992年に一方の池のみを利用した 33頭のうち、27頭(82%)が1993年にも同じ池だけを利用していた。 メスは調査個体数が少ないが、やはりオスと同様に翌年も同じ池を利用 する傾向が強く見られた。オス·メスとも、ヒキガエルの繁殖個体は特 定の繁殖池への執着度が強く、シーズン内で見てもシーズン間でみても、同じ 繁殖池を利用し続けるようだ。ヒキガエルでは他の個体群でも、個体と繁殖池 との結びつきが強いことがよく知られているが(矢野, 1978;奥野, 1984a; 久居, 1987)、個体の繁殖池が何によって決められているかについては、必ずし もよく分っていない。少なくとも、非繁殖期の行動圏とは関係ないようだ。詳 しくは後述するが、非繁殖期の行動圏に近い池に出現すると限らず、わざわざ B池の横を通過してA池にやって来ると思われる個体も少なからずいることが、 繁殖後の分散調査の結果からも分っている(4.4.節参照)。幼生時代に自分の 生れ育った池を覚えていて、成熟後にその池に戻って来ている可能性も考えら れているが、今のところはっきりしたことは何も分っていない。
繁殖池に出現した個体の再捕(目撃)データより、池への出現パターンを個体毎に見 てみると、一度池に姿を現した個体は、繁殖活動を終了し池から姿を消すまで の期間は、原則としてほぼ毎日池に出現していた。オスの出現日数は、個体差 が極めて大きく、1日しか出現せず姿を消す個体も多数見られたが、かなり長 期にわたって毎日池に出現し繁殖活動を行っていたオスも見られた(図8)。 特に繁殖シーズンの長かった1993年には、2週間近くも出現し続けたオスも観 察された。オスの平均出現日数は、1992年には2.1日なのに対して、繁殖シー ズンの長かった1993年には倍以上の4.4日であった。メスの場合は、オスに比 べて池への出現期間が短く、2シーズンともほとんどの個体は1日しか出現しなか った(図8)。
メスの繁殖個体の捕獲率が、オスに比べて有意に低いと推定されたが(表2)、 この原因として、繁殖池への出現期間のこのような性差が関係していると思わ れる。オスは、比較的長時間池に留まり繁殖活動を行うため捕獲(目撃)しやすいが、 メスは産卵の直前に池に現れ、その日の内にオスとペアを形成しそっと産卵を 済ませ、再び上陸して分散してしまう。そのため、どうしても見逃す確率が高 くなるのだろう。
外国のヒキガエルを含め、両生類のいくつかの種や個体群で、繁殖池への出 現時期と体サイズに関係があることが知られている。すなわち、若くて体のま だ小さな個体の出現が遅れる傾向のある場合や、逆に小さな個体が 早目に出現する傾向がみられる場合があることが報告 されている(例えば、Kusano, 1980;Gittins et al., 1980)。日本産のヒキ ガエルでは、現在までそのような報告はなされていない。そこで、山北の個体 群について繁殖個体の体サイズと出現時期の関係を検討してみたが、 1992·1993年の両シーズンともオスの出現時期と体長の間に有意な関係が 検出できなかった(1992年, rs=0.19, N=95; 1993年, rs=-0.02, N=77)。 メスでもオスと同様、両シーズンとも大きな個体が早目に現れるなどの、ある一定の 傾向はまったく見られなかった。
ヒキガエルは繁殖期に繁殖場である池に集合し、そこでオスとメスが出会い、 1対1のペアが形成され産卵が行われる。一般に繁殖個体群の性比はオスに偏り、 なおかつ、オスは比較的長期間繁殖池に滞在しメスを待つが、メスの出現は短くかつ 同調しないため、一日毎の性比はさらにオスに偏る傾向 が強くなる。したがって、産卵前のメスを巡るオス間の競争は厳しいと考えられる。 実際、繁殖シーズンのピーク時には、1頭のメスの背中に複数のオスがしがみ つき団子状になり、他のオスを排除しメスを独占しようとしている状態をしば しば目にすることができる。
図9は、産卵前の受精可能なメス1頭当たりの繁殖オスの個体数(実効性比) を、繁殖シーズン中の1日毎にみた結果である。繁殖個体群の性比(オス/メス) は1.7-2.0程度であるが(表3)、1日毎の実効性比は日によって変動し、かな り高くなることが分る。実効性比の平均は、1992年のA池では 4.28(SD=1.69, N=3)、B池では4.44(SD=2.08, N=3)と池間の差は小さかったが、1993年には、 A池で4.60(SD=2.11, N=10)、B池では11.22(SD=4.79, N=8)と大きな差が見 られた。1993年のB池では3月20日には、実効性比が20近くまで達し、オス同 士のメスを巡る競争の激しさが伺われる。
| 1♀のペア形成 | ペア♂ | |||
| 年度 | 確認回数 | 入れ替り率 | ||
| 0回 | 1回 | 2回 | (2回/1回以上) | |
| 1992 | 14. | 17. | 0. | 0.00 ([ 0/17]) |
| 1993 | 8. | 23. | 5. | 0.18 ([ 5/28]) |
オスは、メスの背中に抱接しペアを形成しても、まだ卵を受精させられると は限らない。場合によっては、メスとペアになれなかった``あぶれオス''が、 ペアに割り込み、メスを奪い取ってしまうことがヒキガエルでも知られている。 日本のヒキガエルでも、10%程度のメスで産卵前にオスの入れ替りが報告さ れている(奥野, 1986a)。ただし奥野(1986a)は、オスの入れ替りは調査に よる人為的な影響によるもので、オス間の相互作用によるものではないと述べ ている。そこで、今回の調査結果からメスのペア形成から産卵までの過程を追 ってみた。標識したメスのうち、1992年には17頭でペア形成を確認すること ができたが、どの個体についてもオスの入れ替りは認められなかった(表4)。 1993年には、ペア形成が確認された28頭のうち、5頭でオスの入れ替りが 観察された。オスが入れ替ったペアについて、最初のオスと入れ替ったオスの 体サイズを比較してみると、体長に関しては、大きいオスに替ったのが3例、 小さいオスに替ったのが2例であった。体重に関しては、重いオスに替ったのが2例、 軽いオスに替ったのが2例、ほとんど体重に差がなかったのが1例であった。 すなわち、小さなオスから大きなオスに替るという、一定の傾向は検出できなかった。 今回の調査でも、オスの入れ替りは、入れ替る現場を直接観察したわけではな いので、``あぶれオス''によるメスの乗っ取りによるもと断定することはでき ない。しかしながら、初回の捕獲時を除き、観察は遠くから個体に触れること なく行っているので、奥野(1986a)のような人為的影響は考える必要はない だろう。
メスは、繁殖シーズン中に1回だけしか産卵することはできないが、 オスの場合は、メスさえ獲得できれば2回以上産卵に関与することが可能であ る。実際に産卵するところまでは追跡することはできなかったが、メスに抱接 しペアを形成するところまでは観察することができたので、ペア形成回数でオ スの繁殖成功を見てみたい。ただし、前述したようなペアオスの入れ替りがあ った場合は、当然のことながら最初のオスはペアを形成したと見なさなかった。
1992年には95頭、1993年には77頭のオスについてペア形成のデータを得るこ とができた。両シーズンともペア形成が確認できたのは約3分の1 (1992年は34%、1993年は32%)の個体のみで、 大多数の個体は一度もメスを獲得できな かった(図10)。オスにとって配偶者を獲得するのは決して楽なことではない ようだ。ただし、1シーズン中に3回もペアを形成できたオスもいて、オス間 の個体による変異が大変大きいことが分る。例えば、No.60のオスは比較的体 の大きなオスであったが(148mm, 267g)、1992年3月12日にA池に姿を現した。 その後、14日にNo.95のメスと抱接しているところが観察され、さらに16日に はNo.124のメスと、19日には未標識のメスとペアを形成した。結局、19日まで 6日間出現し計3頭のメスを獲得した。また、1993年3月19日からA池に出現し たNo.567のオスは、比較的小柄な体をしていたが(120mm, 160g)、21日に未 標識のメスと、25日にNo.111とNo.598の2頭のメスと、26日にはNo.611のメス に抱接していた。ただし、No.111のメスとは、抱接直後にNo.606のオスに奪い 取られたのか、すぐにペアを解消していた。結局、このオスは27日までに 8日間繁殖活動を行い、3頭のメスとペアを形成することができた。
それでは、どのようなオスがメスを獲得できているのだろうか。ペアを形成 できたオスとペアになれなかったオスをいろいろな面から比較してみた。まず、 シーズン中に一度以上ペアになれたオスと一度もなれなかったオスで、体長や 体重を比較してみた。その結果、両者に統計的に有意な差は検出できなかった。 そこで、さらに細かく分析するため、一日毎に池毎に出現していたオスのうち どの個体がペアになっていたのかを調べてみた。この場合もやはり、出現して いる個体の中で大きなオスがペアになりやすく、小さなオスはペアなりにくい という傾向は見られず、大きさに関係なくペアを形成しているようだ (図11, 12)。体長とペア形成の同様な関係は、金沢や東京の港区の個体群でも観察さ れている(奥野, 1986b;久居, 1982)。日本のヒキガエルでは、体の大きさは メスの獲得にそれほど重要でない場合が多いようだ。
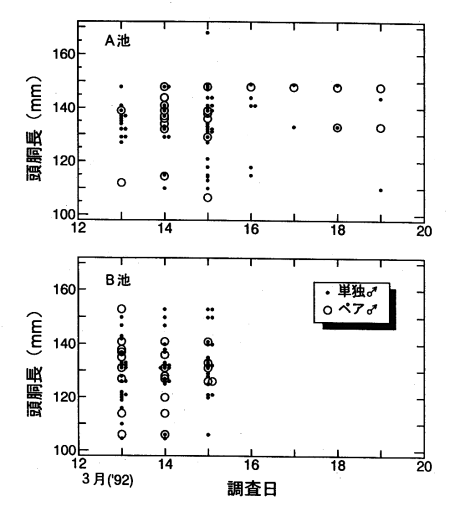
Figure 11: ペアと単独オスの体長の比較(1992年).
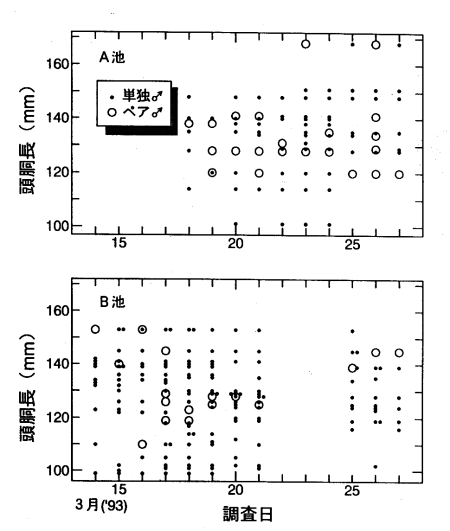
Figure 12: ペアと単独オスの体長の比較(1993年).
次に、シーズン中にペアを形成できたかできなかっただけではなく、何度ペ
アを形成できたのかという量的側面に注目し、それと関係のある要因を幅広く
探ってみた。ここでは、体長(頭胴長)と体重を含め6つの特性とペア形成回
数との関係を分析してみた(表5)。ただし、ここで示した肥満度は、オスの
体長L(mm)と体重W(g)との間の回帰式を求め(N=172, r2=0.78)、
|
この式よりある体長の標準的な体重を計算し、実際の
体重との比の対数値を用いた。また、1993年はメスの捕獲率も比較的高く(表2)、
ほとんどの個体について体長や体重が分っていたので、その体重を用い
てメスの一腹卵数を推定した。メスの体重W(g)と蔵卵数Cの関係は、松井(1987)
のデータをもとに下記の回帰式を求めて用いた(N=14, r2=0.89)。
|
そのため、1993年に関してはペア形成回数だけではなく、オスが授精 した卵数との関係もあわせて分析することができた。
Table 5: ヒキガエル♂の繁殖成功と諸特性の関係(Spearmannの順位相関係数 rs).
| '92年 | '93年 | ||
| ペア形成回数 | ペア形成回数 | 授精卵数 | |
| (N=95) | (N=77) | (N=77) | |
| 頭胴長 | -0.04 | 0.24* | 0.24* |
| 体重 | -0.03 | 0.20 | 0.20 |
| 肥満度 | -0.02 | -0.05 | 0.05 |
| 脛骨長 | -0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 出現日数 | 0.36*** | 0.28* | 0.29* |
| 出現時期 | 0.28** | -0.05 | -0.03 |
| * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001 | |||
表5より明らかなように、ペア形成回数と有意に相関のある特性は意外に少 なく、1992年は繁殖池への出現日数と出現時期、1993年は頭胴長と出現日数の それぞれ2特性に過ぎなかった。そのなかでも、2シーズンとも最も相関の強か ったのは出現日数であった。1993年には、体長もペア形成と有意な相関が検出 された。しかし、この年は体長と出現日数の間にも有意な相関があり、体長が ペア形成に直接影響を与えたと考えるよりも、体の大きなオスはより長く出現 する傾向があり、その結果としてペアを形成することが多かったと考えるのが妥 当だろう。1993年には繁殖シーズンがかなり長期化し、体の小さなオスは長く 出現し続けることが大きなオスに比べて困難だったのかもしれない。いずれに しても、山北の個体群では、オスはできるだけ長く繁殖場に留まり繁殖活動を 続けることが、メスを獲得し子供をより多く残す上で重要であることが分った。
表5で取上げた特性以外にも、オスの繁殖成功に重要と考えられるものがあ る。例えば、年齢や経験はどうであろうか。ヒキガエルのオスは、比較的長生 きし、一生のうち一度だけでなく何度も繁殖に参加することが知られている。 その場合、まだ繁殖経験の少ない若いオスよりも、何度も繁殖の経験を積んだ オスの方が、メスを獲得する上で有利かもしれない。そこで、1992年と1993年 の2シーズン連続で繁殖に参加した38頭のオスの、それぞれのシーズン中のペ ア形成を比較することにより、年齢や経験によってオスの繁殖成功が影響を受 ける可能性を検討してみた。これらのオスたちの平均ペア形成回数は、1992年には 0.42(SD=0.60)であったが、翌年1993年には0.53(SD=0.76)となり、 シーズン間で特に差を検出することはできなかった(対応2試料t-検定, t=0.681, P > 0.5)。また、彼らの それぞれのシーズンのペア形成回数間にも有意な相関は検出できず (rs=0.04, N=38, P > 0.7)、1992年により多くペア形成に成功したオスが、 翌年1993年にもより多くペアになれるとは限らなかった。 しかしながら、年齢や経験の影響を見 るには、2シーズンだけのデータではまだ十分とはいえない。今回の調査で各 個体から得られた指骨により、より多くのオスの年齢を直接推定できれば、こ の点に関してもさらに検討できるだろう。
今まで、主としてペア形成回数を見てきたが、オスの繁殖成功は、ペアにな れた回数だけなく、どのメスとペアになったかが重要になる場合もある。なぜ ならば、両生類のメスの産卵数はメスの体サイズと関係しているので、できる だけ大きなメスとペアになることが子孫をより多く残す上で有利になる。 ペアを形成しているオスとメスの体長の関係を検討したところ、 オス·メスの体長の間には、 有意な相関関係は見い出せなかった(1992年, r=0.07, N=17; 1993年, r=-0.16, N=35)。大きなオスは大きなメスと、小さなオスは小さなメスとペアを形成する といった、サイズに関する同類交配的な傾向は認めらず、 ランダムな交配が起こっていることが分る。ヒキガエルでは、オスの 方がメスに比べて体が少し小さい傾向があるが(図1)、ペアのオス·メ スを見ると、必ずしもそうなるとは限らず、小さなメスに大きなオスが抱接し ていることもたびたび観察された。
ヒキガエルのメスは、一シーズン中に一度しか産卵できないので、メスの繁
殖成功は主として一腹卵数によって決まるだろう。今回の調査では、一腹卵数
を直接調べることはできなかったが、前述したようにメスの体重から一腹卵数
を推定することができる。ただし、体長は捕獲したすべてのメスについデータ
を得ることができたが、産卵前の体重については必ずしも測定できたわけでは
ない。そこで、産卵前のメスについて、体長L(mm)と体重W(g)の関係式を求め
てみた(N=47, r2=0.57)。
|
この関係式より、体長さえわかれば産卵前の体重が推定で き、4.3.3.節ですでに述べたメスの体重と蔵卵数の関係式から、一腹卵数が推 定できることになる。
図1より、メスの体長は110-160mmであるので、一腹卵数は約3,000-6,000 程度であると推定される。その幅は2倍程度であり、残せる子供の数の個体差 は、オスに比べると少な目であると言えよう。メスの平均体長は両シーズンと もほぼ140mmであったので、このことから平均的なメスの産卵数は約4,500卵と 推定される。この値を用いて、調査個体群の総産卵数を求めることができる。 1992年には62頭、1993年には50頭のメスが繁殖に参加したと推定されるので (表3)、それぞれ279,000と225,000卵が産卵されたことになる。
1992年の調査では、総計26頭に発信器を装着したが、そのうち21頭 (♂14頭、♀7頭)について池からの分散過程を追跡することが出来た (表6、図13-15)。以下に、彼らを追跡した結果を個体毎に見てみたい。
|
性別 |
|
|
|
注 | ||||||||
| 1a | ♀ | 135 | 335 | 発信器脱落 | |||||||||
| 1b | ♂ | 149 | 295 | 123 | 5月15日死亡(原因不明) | ||||||||
| 2 | ♂ | 115 | 132 | 137 | 5月29日まで追跡 | ||||||||
| 3 | ♂ | 107 | 136 | 発信器脱落 | |||||||||
| 4 | ♂ | 132 | 225 | 66 | 6月5日まで追跡 | ||||||||
| 5a | ♂ | 139 | 285 | 45 | 3月16日死亡(交通事故) | ||||||||
| 5b | ♂ | 148 | 267 | 96 | 6月27日まで追跡 | ||||||||
| 6 | ♂ | 132 | 215 | 112 | 5月22日死亡(原因不明) | ||||||||
| 7a | ♂ | 112 | 156 | 発信器脱落 | |||||||||
| 7b | ♂ | 126 | 198 | 34 | 5月29日まで追跡 | ||||||||
| 8a | ♂ | 133 | 270 | 73 | 4月17日死亡(原因不明) | ||||||||
| 8b | ♂ | 136 | 269 | 93 | 6月12日まで追跡 | ||||||||
| 9 | ♂ | 153 | 265 | 発信器脱落 | |||||||||
| 10a | ♂ | 119 | 206 | 89 | 3月19日まで追跡 | ||||||||
| 10b | ♂ | 133 | 237 | 27 | 5月9日死亡(草刈り機による) | ||||||||
| 11 | ♂ | 137 | 260 | 178 | 5月29日死亡(原因不明) | ||||||||
| 12 | ♂ | 148 | 267 | 80 | 6月5日まで追跡 | ||||||||
| 13 | ♂ | 137 | 205 | 148 | 5月15日まで追跡 | ||||||||
| 14 | ♀ | 125 | 185 | 34 | 5月9日死亡(捕食) | ||||||||
| 15 | ♀ | 143 | 270 | 発信器脱落 | |||||||||
| 16 | ♀ | 138 | 385 | 86 | 5月29日死亡(原因不明) | ||||||||
| 17 | ♀ | 141 | 288 | 45 | 4月10日死亡(捕食) | ||||||||
| 18a | ♀ | 133 | 193 | 178 | 4月17日まで追跡 | ||||||||
| 18b | ♀ | 128 | 177 | 31 | 6月5日まで追跡 | ||||||||
| 19 | ♀ | 138 | 213 | 260 | 6月19日まで追跡 | ||||||||
| 20 | ♀ | 132 | 205 | 70 | 5月29日死亡(火傷のため) |
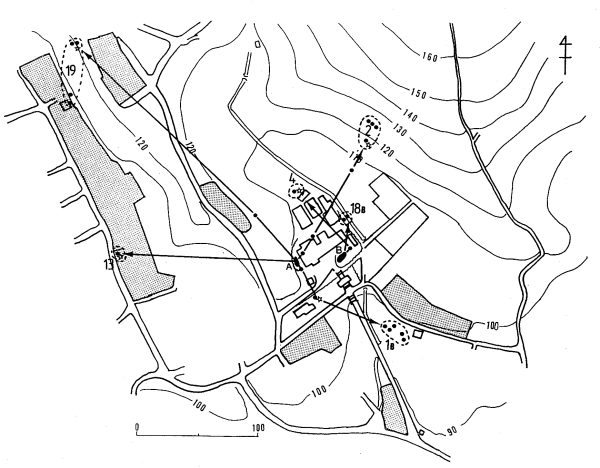
Figure 13:
テレメトリ−法によって追跡した個体毎の繁殖池からの分散ルート(1).
数字は発信器番号(表6参照)を示す. ●は発見地点, ☆は春眠場所,
★は死亡確認地点,
点線で囲った部分は各個体の非繁殖期の行動圏を示す.
地図上の薄い灰色の部分は住宅地域を,
等高線や距離の単位はすべてメートルで示す.
発信器No.16(図14) 3月14日17時30分A池にて産卵後に捕獲されたメス (個体No.75)に装着した。20時00分には20m離れた排水管の出口で確認され、 すでに池から分散していた。15日の7時30分には門の脇の落葉の中に、10時00 分には道路の石垣に移動しており、石の隙間に潜り込んでいた。ここで春眠に 入り、4月10日までほとんど動きが見られなかった。4月17日には移動を再開し、 石垣を出て寺の東側の排水溝の中の草陰に隠れていた。24日にはさらに50m移 動し、草地の草むらのなかで確認された。このメスは、繁殖池からここまで分 散してくるのに、一旦寺の南側に出て大きく迂回したことになる。ほぼ真っ直 ぐ非繁殖期の行動圏に戻っていく個体が多い中、特異な個体であった。その後 周辺の草地で活動していたが、5月29日死体で発見された。
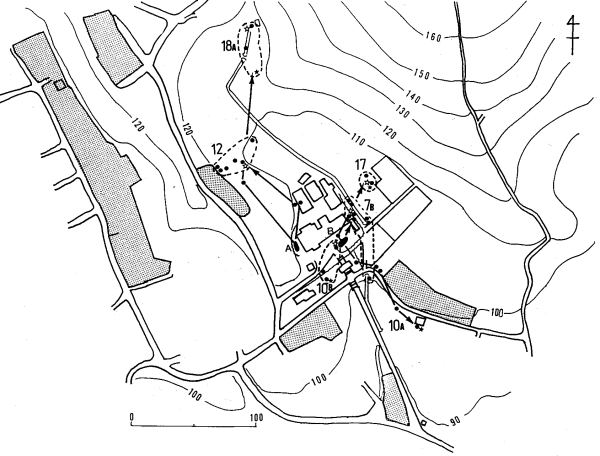
Figure 15:
テレメトリ−法によって追跡した個体毎の繁殖池からの分散ルート(3).
彼らの移動分散の様子を大まかに見てみると、 雌雄による差は見られず、大きく2つの移動パターンに分けられた。一つは、繁殖終了後大きく移動し、その後定着するタイプと、もう 一つは、繁殖終了後しばらく池のそばに留まり、 その後大きく移動を始めるタイプである。この違いは、ヒキガエルが繁殖終了 後の春眠をどこでするかによっている。即ち、繁殖終了後すぐに非繁殖期の行 動圏に戻りそこで春眠するタイプが前者で、すぐに戻らず繁殖場のそばか、ま たは移動途中で春眠に入り、春眠からさめた後、非繁殖期の行動圏に戻るのが 後者のタイプである。春眠場所を確認できた17頭について、非繁殖期の行動 圏と思われる分散後の定着場所との関係を見てみたところ、70%の個体が非 繁殖期の行動圏内で春眠していることが分った(図16)。
春眠期間は個体によりかなり異なり、繁殖終了後すぐに春眠に入り始め、早 いものでは3月の終わりには活動を再開したが、遅いものは4月下旬頃まで春眠 していた個体も観察された。各個体の春眠期間は1週間から3週間で、平均15.7 日(SD=6.0, N=15)であった。何れにしても、5月の初めまでにはすべての個 体が非繁殖期の行動圏に戻り、その後ほとんど移動せずある一定の範囲内に定着した。
各個体の分散過程を詳しく述べてきたが(図13-15)、これらの結果から、 繁殖池から非繁殖期の行動圏までの移動は、一部の例外を除いてほぼ直線的に 行われていることが分った。例えば、発信器No.11を装着したオスはB池で繁 殖後、南に真っ直ぐ移動し行動圏に戻った(図14)。また、メスでも、発信 器No.19の個体はA池で繁殖後、尾根を迂回することなく斜めに横切り、尾根 の反対側に真っ直ぐ一気に戻っていった(図13)。彼らは繁殖池と行動圏の 位置関係を熟知しているように見える。 このような両生類の繁殖場への、および繁殖場からの定位行動 は良く知られていて、どの様にして定位しているのかについて、いくつかの仮説が考えられている。アズマヒキガエルでも、繁殖池に移動してきた個体を他の場所へ人為的に移動し、その後の行動を詳細に観察した実験が行われている。その結果を検討したところ、繁殖個体は、少なくとも池の周囲50mの範囲内では、地理についての記憶をもとに、池への定位を行っていると考えられた(石居, 1987)。また、その地理についての記憶は視覚ではなく、嗅覚が関係しているらしい(Nishio et al., 1988)。
図17には、各個体の非繁殖期の行動圏の分布を示した。般若院の繁殖個体群 の生息範囲は、般若院を中心に四方八方に広がっているが、般若院の北側に分 散する個体が多い傾向が見られた。追跡した21頭の約50%の個体 が、北の谷部へ分散していった。これらの結果より、般若院の繁殖個体群にと って、般若院北側の谷部が現在重要な生息場所となっていることが分った。
各個体の非繁殖期の行動圏は比較的狭いようで、約30m程度の範囲内に留ま る個体が多いようだ(図17)。これは、ヒキガエルの成体は、長期間にわた って特定の比較的狭い範囲内に定着しているという他の個体群での調査結果 ともほぼ一致する(矢野, 1978;奥野, 1985b)。また、奥野(1987)が報告 しているように、山北の個体群でも個体間の排他的関係は観察されず、行動 圏もかなり重複しているようだ。実際、発信器を装着し行動を追跡している 際、同じ穴に2頭のヒキガエルが同居しているところも観察された。
次に、般若院で繁殖した個体がどれくらいの距離を分散して行くのかを知るた め、各個体の非繁殖期の行動圏と繁殖した池の最大直線距離を調べた (表6,図18)。その結果、池から30m程度しか分散せずに池の周囲で非繁殖期も生活す るものから、最大260mも分散して行くものまで見られた。分散距離や方向には、 特に性差は見られず、 50-100m程の比較的池の近くで生活しているものが多く、260m移動した1頭 を除く20頭は200m以内に分布していた。オス·メス込みの分散距離の平均は、 95.5m(SD=59.2, N=21)であった。
日本のヒキガエルの繁殖後の分散については、今までにいくつか報告がある。 そのほとんどは標識再捕調査によるもので、今回の調査のように個体毎に分散 過程を詳細に追跡したものではないが、それらの結果と比較してみたい。東京都港区 の自然教育園におけるアズマヒキガエルの調査では、オス·メスによる 差はなく平均150-250mで最大500mであった(矢野, 1978)。金沢のニホンヒ キガエルのメスでは、平均100mで最大195mであったという(奥野, 1986a)。 東京都港区と金沢の調査地は、いずれも隔離された場所で閉鎖個体群を対象に行われ、 その影響を受けている可能性が考えられる。例えば、八王子の開放的な場所で 調査した金井(1971)は、一例だが1,500m移動した個体がいたことを報告して いる。しかしながら、今回の開放的な個体群での調査でも、前述したように意 外に分散せず、東京都港区や金沢での調査とほぼ同じような傾向が見られたことから、 ヒキガエルはそれほど遠くまで分散することは少ないように思える。繁殖池の せいぜい200-300m以内の範囲内に生息していることが多いようだ。
池などの止水で繁殖する両生類では、孵化から変態までの幼生期に、水生昆 虫·魚類·イモリ(Cynops pyrrhogaster )など他の両生 類·ヘビ類などの捕食により高い死亡率が観察されることが多い。しか しながら、変態後ある程度まで成長すると死亡率も低下し、金沢のヒキガエル などでは、2歳以降の年間の生残率が40-90%とかなり高い値を示し、10年以 上も生存している個体もあるという(奥野, 1985a)。今回の調査でも、 1992年には指切りによる個体標識を行ったので、1992年と1993年の間での繁殖個体 の生残率を推定できた。
1992年にはオス·メス併せて126頭の繁殖個体に標識したが、その内 49頭は翌年の繁殖シーズンに再び捕獲することができた。すなわち、再捕率 は約40%となった(表7)。細かく表を見てみると、メスの方がオスに比べて 再捕率が低いように見えるが、この差は主として捕獲率の差によるもではない だろうか(表2)。また、表7の再捕率をオス·メス間で統計的に検定し たところ、有意な差とは見なせなかった(Fisherの正確確率検定, P=0.52)。 生残率や毎年の繁殖参加率が、ヒキガエルのメスではオスに比べて 低くなる傾向があるとい う報告もあるが(奥野, 1985a;久居, 1981)、山北の個体群では再捕率に性差 が検出できず、そのような傾向は認められない。
| 性別 |
|
|
|
||||||||
| ♂ | 95. | 39. | 0.411 | ||||||||
| ♀ | 31. | 10. | 0.323 | ||||||||
| 総計 | 126. | 49. | 0.389 |
メスは卵の生産のために多量のエネルギーを必要とするため、個体群によっ ては繁殖を毎年することができない場合があることが知られている。しかしな がら、山北では前述したように比較的メスの再捕率が高く、オスと差が見られ なかったことから、繁殖を休む個体がまったくいないとは断定できないが、多 くのメスは毎年繁殖に参加していると思われる。また、調査地である般若院の 付近には、他にヒキガエルの大きな産卵場がないので、よその産卵場へ出現し ている可能性も低い。そこで、年間の生残率は、再捕率を捕獲率で割ることに より推定できる。表2より、1993年の捕獲率は70-90%であるので、生残率は 約50%と推定される。
この値は、約半数の個体が翌年までに死んでいることを示している。両生類として は決して低い値ではないが、ヒキガエルのように体が大きく、かつ毒をもって いるカエルにしてはそれほど高い値でもないような気がする。実際、発信器を 装着して繁殖後の分散を追跡した際も、我々は、多くの個体が様々な理由で死 亡していることを観察している。例えば、追跡した21頭の内、自動車による 分散途中の轢死、タヌキなどの獣による捕食、草刈り機による切断事故、焚き 火による焼死や原因不明(一部農薬等が関係している可能性もあるが)などで、 10頭が7月までに死亡したのを確認した。死亡の多くは、春から夏にかけて の繁殖後の比較的短期間に集中しているように思える。年齢推定で最も老齢な 個体の年が、6歳であったことも併せて(図2)、山北のヒキガエルはそれほど 長命とは言えないかもしれない。
標識再捕調査のデータより、繁殖個体の一年間の成長を分析した。繁殖個体 の年齢の節(4.1.2.節)で述べたように、ヒキガエルの変態直後の成長は極めて 速く、1歳で100mm近くまで成長する個体もいるが、成熟後は成長がかなり低下 すると思われる。実際、体長の年間平均成長率は、オスで5.8mm (SD=6.9, N=38)、メスで1.8mm(SD=6.2, N=10)と 体の大きさの割には小さいことが分った。 また、体長と成長率には負の相関が見られ、体が大きくなればなるほど、成長 率も減少した(図19)。この関係には、オス·メスで違いが見られず、 同じ回帰直線上にのっていることが分る。つまり、同じ大きさの繁殖個体同士 で比べると、オスもメスも成長率に違いがなかった。また、この回帰直線から、 体長が150mmを越えたところで成長が止ると推定されるが、実際の体長分布で も最大個体の体長は150mm強で、ほぼあっているように見える(図1)。
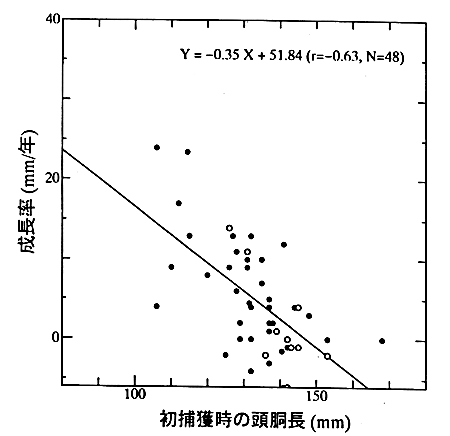
Figure 19: 繁殖個体の体長と成長率の関係. 黒丸はオスを,
白丸はメスを示す.
1992年3月から1993年4月まで、主として2回の繁殖期を中心にアズマヒキガエル (Bufo japonicus formosus )の繁殖個体群の調査を神奈川県足柄上郡山北町 岸1640番地の般若院において行った。その結果、以下のことが明らかとなった。
1192-03 八王子市南大沢1-1 都立大·理·生物 (2010年現在、192-0397、首都大学東京・理工・生命科学)
2251
藤沢市辻堂西海岸1-5 RK58
File translated from TEX by TTH,
version 3.01.
On 3 Sep 2001, 16:32.
| なおこの内容は下記の報告書の一部を抜粋したものです(pp.5-31)。 神奈川県指定天然記念物「山北町岸のヒキガエル集合地」におけるアズマヒキガエルの生態調査報告書(1993年、山北町岸のヒキガエル生態調査団、35p) また、この調査の結果は下記の論文でも詳しく報告されています。 必要な方は草野まで請求してください。
|